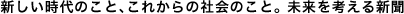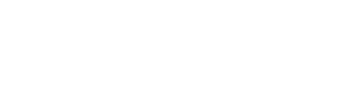北九州を中心に孤立困窮者の生活再建を支援するNPO法人、『抱樸』の活動に参加させてもらった。以前は支援される立場にあった人たちが、生き生きと支援する側にまわり、お互いを朗らかに支え合う様子が印象的だった。孤立無援の場所から、彼らがどうやって立ち直ることができたのか。活動のなかから見える、わたしたちの社会に足りない包容力について、代表の奥田知志さんに聞いた。
この人には何が必要か、この人には誰が必要か
後藤「奥田さんの抱樸という活動を昨日から、見学させていただいて。まずは、奥田さんの活動についてご説明いただけたら、ありがたいんですけれども」
奥田「私たちの団体というか、これ実は抱樸って名前になったのは、名前2回変えてるんですね。最初は『北九州越冬実行委員会』という名前で冬を越すという意味だった。ホームレスの人たちの支援だったので、ともかく生きて春を迎えようで、やりだしたんですね。だから私の大学の先生は当初は南極行ってるんだと思い込んでて」
後藤「南極に(笑)。越冬だからってことですね」
奥田「そうそう。だから奥田君、いつ行ったんだと言うから、毎週金曜日行ってますよって言ったら、毎週行けるのかって言うから、いや、行こうと思えば毎週できますよという話で。よく聞いたら南極越冬隊だった。その名前から『北九州ホームレス支援機構』となって、今、『抱樸』なんです」
後藤「はい」

炊き出しの日の深夜に行われるパトロールの風景。暗がりで奥田夫妻の到着を待ち構える困窮者も。
奥田「ざくっと言うと、ホームレスの支援から始まったんですが、そういうホームレスという枠組みで人を見るのはやめようと。そういうのを者別(シャベツ)なんて言い方しますよね。障害者とか、高齢者とか。その者別(シャベツ)で人を見るのやめて名前のある個人として、その人と関わりましょうというのが基本スタンスで。そうなると、この人には今は何が必要なのか、同時に、この人には誰が必要なのか。そういう問いの中で事業がどんどん大きくなって、今は職員も100人を超えるような」
後藤「なるほど」
奥田「ホームレス支援から始まって、今は子どもの支援もしています。例えばホームレス状態の人の子ども時代の話を聞いたら、やっぱり子ども時代から大変なんですね。だったら、もう子どもの頃から支援の体制つくろう、という。この人には何が必要か、この人には誰が必要かという、そういう問いの中で、どんどん事業ができてきた。今、27の事業になってまして。今年で35年目を迎えるNPOです」
後藤「知志さんの本を読ませていただいて印象的だったのが、僕たちはいつも“ホームレス”みたいな言葉をざっくりと使っているわけですけれども、単純に家がない人というのは“ホームレス”というより、まず“ハウスレス”なんじゃないかと。そして、“ホーム”というのは家のことじゃなくて、“つながり”のことなんだということが書かれていて。この “ハウスレス”と“ホームレス”の違いについて書かれてたことが、はっとする内容でした。活動の中で、いつくらいに気づかれたことなんですか?」
奥田「これは最初35年前に始めた頃は私も当時まだ25歳ぐらいでしたから若かったんですけれども。見た目の問題というのは家がない。お金がない。その背景としては仕事がない。ともかく家とお金、何とかせんといかんということで始まったんですね。でも結局おうちに入られて、もうこれで安心ですねと。現に路上にいる時は畳の上で死にたいって、よくおっしゃってましたよ。ほとんどの人がそう言ってたので。何とかアパートに入って、これで一安心ですねって言いたかったんですが、その時点で俺の最期は誰が看取ってくれるやろうかという次の問いが出てきたんですね」
後藤「はい」
奥田「だから、その家がないのをどうするんだというモノの問題と、俺の最期は一体、横に誰が居て看取ってくれるのかというヒトの問題が、最初の段階で指摘されたり。あるいは、その家がないという問題が片付いても、訪ねていくとぽつんと家の中で独りぼっちで。もう仕事も決まったし(路上生活とは)隔世の感なんですけども、ぽつんと独り座っている姿が、小倉駅のあの西通路ってあるでしょう。当時、あそこに50人ぐらい寝てて。段ボールを敷いてポツンと座っている日の姿と、ほぼ変わらないんです。一体これは何が解決できてて、何が解決できてないのかという。人間が生きるうえで、そもそも家やお金や物は絶対必要なんだけども、逆に言うと、それだけで人は生きれるのかという」
後藤「確かに」
奥田「その問いは大きかったですね」
つながりを失うことで奪われるもの
後藤「支援の活動の文章を読んで、知志さんとのつながりができてくると、その支援されている方も意欲が湧いてくるという話が印象的でした。もう私は刑務所に行かないみたいな。そういう変化が見られるところが、非常に響いてくるというか。ああ、人間って、つながりがなくなったり孤立したり、無縁になっていくことで、本当の意味で社会から排除されてしまうというか」
奥田「そうですね。社会からの排除と、同時に、やっぱり自分自身からの疎外みたいなもの。要するに諦めですよね。もう自分はどうでもいいんだという」
後藤「自分自身を諦めてしまう…」
奥田「だけど、長くホームレス支援の現場とか、あるいは虐待の中で生きてきた若者たちと出会うと、『もう俺、どうでもいいから、ほっといてくれ』と。だって家もないし食べ物もない、お金もない人のところに、われわれ、お弁当持っていくだけじゃなくて、家を何とかしますよ。就職も世話しますよ、って言うんですよ。だけどね、普通に予測して一般的に考えると、極端に困っている状態だから直ぐに『待ってました、よろしく』って言うかなと思ったら、これが言わないんです。行っても行ってもね、『いや、ちょっと、また考えとくわ』とか『今度でええわ』みたいな話になって。そこでずっと考えていたのは、人がもう一回、生きようと思う時に、何が足らないんだろうかと。最初は私、単純に物理的な条件だと思った」
後藤「条件の問題ですか」
奥田「家が狭いとか、紹介する家が古いとかね。就職の時も、もう30年前は、ホームレスだって分かって野宿者だと分かって雇ってくれるオーナーさんって、いなかったんです。かといって、うそをついて履歴書を書くわけにもいかないので」
後藤「そうですね」

炊き出しとパトロールの時に配られる「かわらばん」。支援にまつわる情報を掲載。
奥田「だから正直に『実は今、野宿で、もうすぐアパート入って、そこまで生活の見守りもちゃんとします』ということで、やっと雇ってもらえるんだけども、やっぱり条件がよくないんですよ。いくら30年前でも手取りが10万そこそこ。(就労支援を受け入れないのは)やっぱり給料安いからかなと。けど、やっぱり違ったんですね。どんないい条件を持っていっても立ち上がらない」
後藤「仕事と、いい家というだけでは『行きます』ということにはならないってことですね」
奥田「そうそう。そこに何がなかったかというと、“その気”なんですね。意欲というか」
後藤「そうか。意欲というのは、そこまで追い詰められたりとか、何かつながりをなくすと内側から湧いてこなくなっちゃうものなんですね」
奥田「たぶん、だけど、そういうのってゴッチさんたちがされている、創作的なこととかそういうのにしても、ある意味ベースは自己表現だったり自己実現だったりするでしょうし。けど一方で聴いてる人たち、そのつながっている先の人たちの、たぶん思いとか熱みたいなものが、相互に作用しているんじゃないかなって思うんですよね」
後藤「そうですね。偉そうに、自分のつくりたいものをつくる、みたいなことを言っちゃうこともありますけれども、やっぱり届く先のことは信頼しています。音楽を作った先のリスナーのことを想像することによって、はじめて作品になっていくというか。もちろん創作の意欲も湧いていくというか。僕の場合は、仲間が喜んでくれることが大きな動機になってますけれど」
奥田「やっぱり、そこですよね」
奥田「基本的には、人間って自分自身の欲ですよね。いい意味で、その欲が人を動かしていく。かっこいい服着たりとか、このかっこいい帽子欲しいとか。だからこそ働こうという。それは内発的な動機とか意欲なんだけども、じゃあ、それだけで生きているかというと案外そうでもない。もっと言うと、野宿とか、その極端な困窮状態の中で、もう、そういう気持ちが潰えている人たち。ホームレスもそうだったし、小さい頃から虐待を受けてきた若者たちも、『もうどうでもいい命だ。もう私なんか生きてても死んでても、どうでもいい。誰も喜ばないし誰も悲しまない』と。そこまでいった人は中から出てくるものが、もうなくなっちゃってるんですね。普通の感覚の人からすれば『この人、なんで、支援を断ってるんだろう。ああ、ホームレスって意欲がない人たちなんだ』と」
後藤「そういうふうに見られてしまう」
奥田「好きでやってるんだと。もう30年前、みんなそう言ったんですよ。ホームレスなんて結局、好きでやってるんでしょと。それが証拠に奥田さんたち行っても、待ってましたにならないじゃないと。ということは喜んでやってるんでしょと。けど僕、横で見てたら喜んでできるような状況じゃないんです」

市販の薬やカイロ、防寒具などの配布物を持って街を見回るパトロール参加者たち。
後藤「そういう現実があるんですね」
奥田「外で寝て、ごみの中から拾ってきたものを食べながら命をつないでいるわけでしょう。お風呂も入れないし。どう見ても楽しんでやっているようには見えない。好きでやっているようには見えない。じゃあ何が足らないのか。やっぱり、その意欲なんですよね。だから、やっぱり喜んでくれる仲間というのが、いない。もっと極端に言うと死んでも誰も悲しまない。そうなると、もうどうしようもない」
後藤「……」
奥田「そうなった時に、その仲間の存在とかリスナーの存在と同じように、何か外から入ってくるような、私よく言うのが、外から差し込んでくる光のようなものが人間には必要で。それは、ある意味、宗教的な感覚かもしれないけども。何か自分の中だけで成立するんじゃなくて、神様でも仏様でも何でもいいんだけども、何かそういう意志みたいなものが『俺はお断りしてるんだけども、向こうは、いやいや、いやいや、生きないかんで』みたいなね、『生きてほしいんやで』みたいな話が。その外発的なものを支えてきたのが従来はやっぱり家族の存在だったり、仲間の存在だったり。そういうのがもういなくなった人たちだから、そういうような存在になれるかが勝負だったんですね」

NPO法人抱樸理事長、東八幡キリスト教会牧師
1963年生まれ。関西学院大学神学部修士課程、西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ卒業。九州大学大学院博士課程後期単位取得。
1990年、東八幡キリスト教会牧師として赴任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス支援」に北九州でも参加。事務局長等を経て、北九州ホームレス支援機構(現 抱樸)の理事長に就任。これまでに3700人(2022年3月現在)以上のホームレスの人々の自立を支援。