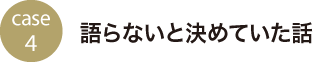この記事は「東北の学生にしか作れない記事を作りませんか」という僕の問いかけに応えてくれた6人の大学生による、それぞれの震災とこれからについてのインタビュー集です。僕の目論見では、彼らはその若さと機動力と時間を目一杯に使って東北の様々な場所をフィールドワークし、言葉を残すのだと想像していました。ところが、彼らが考え、悩み、何度も話し合って選択したのは“当事者としての自分たち”について語り合うということでした。
自分たちにしかできないことは、果たして自分たちを語ることだけなのか、という問いもあると思います。やや、自意識が強いように感じるかもしれません。けれども、震災から2年半が経とうとしている現在、もう一度震災と自分について考え、語り合ってみたいという彼らの誠実な態度に僕は心を動かされました。 僕たちはそれぞれの場所で何を語り、何をすればいいのだろうか。そんなことを考えさせられるこの記事を、特集「震災を語り継ぐ」の最後に掲載します。
震災ボランティアって、流行りものみたいで嫌でした。それが義務みたいに言われることに抵抗があったし、“被災地に住む私たちは、楽しいことをしちゃいけないの?”って。そんな私でも“いつかは何かをやるだろう”ってぼんやりとは思ってたんです。そうして “いつか”の未来の自分に“何か”を押し付けていたように思います。
震災後の6月にチャリティ・ライブがあり、アジカンのゴッチが仙台へ来たんです。生で『ソラニン』を聴いて泣きました。でも、ゴッチがした話の内容はよく覚えていなくて。おそらく被災者を励ます感じの話だったと思います。話を聞きながら涙を流す子を見て、私はドキッとしました。岩手の実家に大きな被害はなかったし、仙台でも震災の傷跡を身近に感じていない私は、彼が励まそうとしている“被災者”じゃない。そんな自分がこの場にいるのは失礼かもしれないと思ったし、泣いている子に申し訳なかった。でも、あの場にいた大多数が私みたいな感覚だったんじゃないかなと思います……。
掲載されている他の3人は何かをしたり、考えたりしてきた人です。自分と彼らを比べて卑屈になったこともありました。でも、自分に出来ることは、そんな自分について話すことだと気づきました。そうすることによって、読んでくれた人に伝えられるものがあるかもしれない。やっと私は“何もしてこなかった自分”から、“何かをしようとしている自分”に変われたような気がします。
2011年4月、僕は震災の傷跡の残る仙台で大学生活をスタートさせました。でも、東京の大学に行きたかった僕は、仙台での大学生活を心から楽しめていなかったんです。東京に進学した友人の話を聞くにつけ、彼らがもう届かない存在のように感じていました。
悶々と大学生活を送る中で“仙台でしかできない大学生活を送りたい”という感情が芽生えてきました。そこで見つけたのが震災復興に関わる、学生を中心とした団体でした。そこに所属して活動を始めた僕は、かつてないほどの充実感を感じ、“仙台に進学した自分”をいつしか肯定できるようになっていました。充実した大学生活を送り、将来は当初の希望通り、出身地である関東に戻り仕事をしたいと考えています。
そんな僕には、ある強い罪悪感があります。それはたとえば、自分の大学生活を充実したものにするため、さらには仙台に進学した自分を肯定するために震災を“利用”したのではないかということ。さらには、震災に関わる活動をしておきながら、4年間が経てばそれを投げ出して、関東に戻って仕事をするという人生設計を貫くこと。これらについての強い罪悪感です。
でも、たった4年という時間でも仙台に住み、震災と向き合った事実は、この先、どこで何年過ごそうとも消えることはないと思います。望む望まざるに関わらず、震災は僕の人生に入り込んで来たし、それはこの時代に生きる人は皆そうなんじゃないだろうかと考えています。
大学1年のときに二度、海外へ行きました。復興予算から旅費の多くを出してもらった、震災を伝えるプロジェクトでした。そういう活動に参加して“他の学生とは違うんだ”という勝手な優越感を抱いていました。でも、自分が伝えたのはインターネットで探せば誰にでも見つけられる情報ばかりでした。“自分自身の震災”にきちんと向き合わずに、どこか震災を利用しているような、そんな負い目や引け目を感じていました。
震災から2年以上経って、今回の企画ではじめて“あの日、何をしていたか”を自分の口から話しました。バンドの練習中に地震が起きたこと。割れたワインの匂いが立ち込めたコンビニの店内。ラジオのアナウンサーが言葉を詰まらせていたことや、星が綺麗だったこと。話したいことが溢れ出して、気づいたら泣いていました。辛い体験を思い出したからでもない。自分と向き合ってこなかった後悔でもない。それはきっと、話を聞いてくれた仲間への“感謝”なんじゃないかと思いました。なんとなく、大学の友達や家族ともこんな話はできなかったけど、ここで話せたことでやっと、“自分自身の震災”と向き合えた気がします。
震災で、自分の人生というほど大袈裟なものではないにせよ、何かが少し変わったと思います。明日、何が起きるかすらわからない。だから“今”と向き合い、今ここでやれることを続けていこうと思います。
俺は、津波で吹奏楽部の同級生を亡くしました。当時、連絡がとれていないのは彼女ひとりで……。覚悟はしていました。ただ、事実を前にしても具体的な感情が湧かず、友人のように泣けない自分を薄情者だとも思いました。
大学からトランペットを始めた彼女は津波から逃げるときにも、アルバイトで貯金して買ったばかりの楽器を背負っていたとうかがいました。一緒に逃げたお兄さんは助かったけれど、彼女は助からなかったそうです。もし重い楽器がなければ、助かったのかもしれません。そう思うと、やるせなかったです。
この話は、語らないと決めていたんです。話したいと思っていたけれど、話すことができなかった。彼女の音楽に対する想いを伝えようとして、“お涙頂戴”の物語にされるのが嫌だったというのもあります。また、語ってしまうことで、自分を“かわいそうな被災者”であるかのように錯覚して、自分に酔ってしまうのが怖かったんです。彼女に対しても、不誠実だと思っていました。
でも、地元を離れて、震災が“非日常”になっている場所に行ってみると、“かわいそうな被災者”という扱いを受けました。語る、語らないに関わらず貼られてしまうレッテルがあります。だからこそ、地元・仙台にいるうちに語りたいと思いました。俺の言葉は、彼女の想いを伝えるには十分ではないかもしれないけど、彼女の音楽に対する想いを届けることができるかもしれない。今回は、その記念すべき第一回なんだと思います。
学生たちのインタビュアーズ・ノート
私たちは、メンバーの思いを受け取って、それを伝わる形に編み直すのが役割でした。冷静に、客観的に話を聞くことが求められていました。でも、彼らの口から語られる言葉は、どれも他人事とは思えないものでした。客観的に見ようとしても、自分の主観がどうしても入り込んできてしまう。私たちは、無遠慮に彼らの心中に土足で踏み込み、いたずらに傷つけているだけなのではないか…。葛藤は常につきまといました。
それでも彼らは、ありのままをさらけ出して語ってくれました。取材の後、「話して良かった」と言ってくれました。“誰かに伝えたい”と思える言葉を、たくさん託してくれました。文字数に限りがある以上、伝えたくても伝えられないことのほうが多いです。そもそも私たちはプロではないただの大学生ですから、彼らの想いを十全に伝わるような形にはできなかったかもしれません。それでも、このページが完成して、読んだときに彼らが抱えるものが少しでも軽くなっていたとしたら、彼らに報いることができたと言えるのかもしれません。
震災について語る場というものは、日常にはなかなかないかもしれません。でも、過剰なタブー視をすることなく、軽んじることもなく、等身大の“自分自身の震災”について語ってみることで、見えてくるものがあるのではないかと私たちは思います。