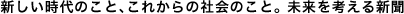中沢 「僕と同じ考えだなぁ。まったくそのとおりだと思います。農業と音楽は似ているんです。農業も音楽も、本来は人間の計画どおりにはいかないんですよね。たとえば農業は、人間がプログラムを立てても、そのプログラムどおりにはいかないようにできている。なぜかというと、必ず自然側の応答がないとできないものだから。人間がプログラムを作って呼びかけを行って、それに対して自然が応答する。この呼びかけと応答が上手くいかないと、農業は上手くいかないんです。だから自然の側の呼びかけとして『そうじゃなくてこうしてください』って要求している場合は、人間は人間の側の思いどおりにはしちゃいけない。要求を引っ込めて受動的になって、自然の側に三歩も四歩も譲歩して、自然が求めていることをしなくちゃいけない。でも、自然の側も自分勝手なことを要求してるわけじゃなくて、人間の求めに応じて何かを渡すんです。その呼びかけと応答を上手い言葉で言えないかなと思って、内田(樹)君との対談集で“贈与”という言葉を使ったんだけど。だけど、今の企業化された農業や音楽産業について考えてみると、人間がプログラムを完全に作っている。しかも、そこにコマーシャリズムが入ってきた場合、どうしたらウケるかっていう考えが入り込む。そうすると、予測をして、それに合わせてプログラムを作っていくということをやっていく。つまり、自然界に対して人間の要求を全部押しつけていく形になりますよね。それが進んでいくと、自然は人間がやることに全部従っていかなきゃいけない。従わせるということは、自然は単なる素材であり、原材料でしかなくなってしまう。企業化された農業が、まさにそうだよね。自然が高い収益を上げるための素材になっちゃっている。ところが農業っていうのは、そういうものじゃなくて、本来は呼びかけと応答で作られている」
後藤 「なるほど」
中沢 「僕は、その呼びかけと応答ということこそ、“アジア”っていう言葉の含んでいる一番大きな意味なんじゃないかと思ってきた。ベースは狩猟採集だったけれど、アジアというものが形成されていったのは、やっぱり農業なんです。アジアの広大な農業地帯に作られたどの古代文明も、どこか自然に対して受け身なんですよ。自分のプログラムは完全に適応しないし、できないっていう考え方がある。その微妙な行き来の中で、文明ってものが作られていった。それが日本列島に渡り、エッセンスみたいになっているわけです。日本文明って、ある意味でいうとアジアの農業系文明のエッセンスだなと思う。その象徴的なものが“里山”なのかなって。里山って、山でもなければ里でもない、中間状態を作ってます。“中間状態”っていうのは、人間にとっては美を感じさせ、動物にとっては最適な環境なんです。田んぼができてから日本列島に住み着いた動物ってたくさんいて。スズメなんて殊にそうだし、ナマズとか、トンボとか、昆虫類のたいがいはそう」
後藤 「水生昆虫ですね」
中沢 「そう。水生昆虫は、里山がないとダメなんですよ。里山を見てると、自然の要求を受け入れてますよね。動物の要求も植物の要求も受け入れてる」
後藤 「僕が小さい頃は、河川ってそこまで護岸されてなかったと思うんですよね。水田の水路、灌漑って、ホント芸術だと思うんですけど…。僕の地元の田舎でも、子供の頃はまだコンクリートの側溝にしてないところがたくさんあって。そこではフナが卵を産んで繁殖していました。川がどんどん護岸されて、カニもいなくなったし、ハヤみたいな淡水魚もいなくなった。水門なんか、今やゴムみたいなものを膨らませてせき止めたりしていて。いろいろな場所で過剰な線引きがなされているというか。たとえば水田の水路などをコンクリートで作ってしまうと、完全に生物を拒絶するところがありますよね。それが、音楽の四角四面化と、僕は似ていると思っていて」
中沢 「本質は同じじゃないですか。だから僕は、後藤君が“音楽と農業”について考えてるということは、すごく正しいなと思った。なぜなら、音楽って人間の芸術活動、表現活動の中で“一次産業”だと思っているから。一次産業というのは、ようするに感覚、内面から沸き立って動いてくる感覚や、インテンシティー(感情の激しさ)とかに直接触れているじゃない? だから、音楽と農業っていうのは、根本的に一次産業としての共通性を持っていると思うんですよ。そこで大事になってくるのが、一次産業というのは自然のサイクルに直接繋がっているわけですから、本来はお金にならないということなんです。農家がどうして貧しくなっちゃうかというと、農業ってのは半分は自然の循環サイクルじゃないですか。反対に工場で作るものっていうのは、材料を集め、設備を作り、労働者を雇って作る。ある意味、お金で全部交換しているわけです。ところが農業の一番基本的な部分、“作物が育って実がなる”というプロセスには、お金が関与してないでしょ。自然循環サイクルで富が直接増えていく。もちろん設備費が必要で、種、肥料などは買ってこなきゃいけない。でも、昔の農業は、それすらいらなかった。そして、できた作物に値段をつける場合、人間は自然に軽く働きかけをやるだけって感覚があるから、材料費と労働力ってことになって、計算するとダイコン一本100円ってことになっちゃうわけでしょ。でも本当は、お金に換算できない、自然がやっている部分が入ってくる。僕はね、音楽もそうじゃないかと思っていて。音楽は一番ベースのところで、感覚の一次過程みたいなものに触れている。これは“人間の中の自然”なんですよね。自然を直接組み立てて作品を作ってるわけです。だから音楽は本来、お金にならないはずなんです。お金をもらうとしたら、昔のミュージシャンみたいに箱を置いておいて、そこに入れてもらうのが原型なんじゃないかって。これもつまりは“贈与”だからね。聴いた人が何か音楽の贈り物をもらって、それに対してお返しをする。いくらと金額は決まってない。そういうのが音楽本来の形態だと思う。でも、それが20世紀になって大産業になっていった」
後藤 「そうですね」

中沢 「すると、企業化された農業と同じで、もうこれは農業じゃないよってことになるわけです。もう完全に自然をコントロールしちゃって。企業は『これだけの農薬を撒いたから、これだけの肥料を注いだのだから、これくらいの収益を出せ』って、自然に対して要求するわけですよね。何から何まで貨幣換算ができるもので、農業を組み立てようとしている人がいるわけじゃないですか。だから今の音楽産業…崩壊しかかっている音楽産業と農業って、似てるでしょ? これは本来、産業にならないものを産業にしたからなんですよ」
後藤 「たしかにそうですね」
中沢 「だから、システムとしては当然のごとく崩壊していく運命を潜めています。農業というのも、今の資本主義社会の中では、自然サイクルを自分の中に取り込んでいる分、どうしても貧しくなっちゃう。すると、やる人が減ってしまう。そういう過程で、滅亡の道を歩もうとしているかに見えたけど、今、農業は盛り返そうとしてるでしょ?」
後藤 「そうなんですよね」
中沢 「それは何かっていうと、20世紀文明…お金に換算していく文明が、大きいサイクルで色々なところで崩壊を起こしちゃってるってことを、むしろ若い世代の人たちが直感で感じてるってことだと思うんだよね」
後藤 「資本主義や貨幣については同じように考えますね。やっぱり、マルクス(※6)の本を一度ちゃんと読もうかなって思います。古典にはもしかしたら新しい読み方があるのかなって」
中沢 「あると思います。ただマルクスは、農業のことを切っちゃうんです。それが社会主義の最大の問題点で、農業のことをわかってない。実はマルクス以前の経済学の人たちの中に、農業を研究してる人たちがいて、その人たちの理論を考えてみると素晴らしいんです。でも、18世紀の時代遅れの考えだと否定されてしまった。だけど僕は、彼らの理論をもう一回復活させないと、人間の世界の経済は甦らないと思うんです。だから、農学校を作ろうと思っていて。いわゆる農業技術を教える人たちはたくさんいると思うけど、そうじゃなくて、今日僕らが話しているようなこと、“音楽って何なのか”、“音楽と農業って一体どう関わりがあるのか”とか、“農業って、人間のやる行為のひとつとしてどういう意味を持っているのか”とか、そういうことをちゃんと教える学校を作りたいなと思ってるんです。後藤君、協力してくれません?」
後藤 「はい、喜んで」
中沢 「音楽と農業ってものすごく本質的な部分で、本当はものすごく近い。そして、人間の世界が甦ってくるための条件のひとつは、“アートが甦ってくる”ということなんですね。アートの中で、音楽が真っ先に産業として崩壊を始めているじゃないですか。そこから何か出てくるかなと思ったら、後藤君たちみたいな人が出てきて、音楽の世界にも希望を感じてるんですよ」
後藤 「実感として、若いミュージシャンたちが音楽だけでは食えなくなってる現象が起きていて。このまま、ありものの産業に乗っかっていても、どうしようもないというのは、みんなわかってるんですね。やっぱり貨幣ってものが、いわゆる“価値”って感覚に過剰に入り込みすぎてて。貨幣価値ですべてのものを計れるかのような錯覚が蔓延してるのが、怖いっていうか」
中沢 「そうだね。でもほら、“都市”って何かというと、お金で生活する人たちの集まる場所の意味ですから。自分が必要とするものを大地からもらったり、あるいは人からの贈与、贈り物で生きたりしないで、全部お金で換算するって空間が都市なんです。都市って元々は市場、マーケットなんですよ。マーケットに人が集まってきて、だんだんそこが膨らんで、都市ができたんですね。都市の人たちは王様を作り、その人に権力を渡して自分たちはマーケットの中で暮らすようにした。それが、近代社会です。それに対抗していた権力が誰かっていうと封建領主。だからよく、封建領主は古いって言うけど、そういうものじゃないんですよ。封建領主への地代って、米などの物納でしょ。つまり、自然循環に沿っている。ところが城壁の中の都市は、物納でなくお金なんです。結局、都市側が勝利しちゃったので、価値として、ありとあらゆるものがお金で換算できるようになってしまった。だから、お金がないともう生活できない。生きてくことすらできない空間が都市なんですね」
後藤 「なるほど」
中沢 「この都市が作り上げた文明っていうのは、ある意味で言うと、お金の文明で。そのあたりをマルクスが克明に分析したんですね。その限界点に来ちゃったのが20世紀の終わりから21世紀かな。産業的にまず何が崩壊したかっていったら農業です。崩壊した農業を、どうやって生き延びさせていくかということで、企業化が始まった。モンサント(※7)とかが、種子から農薬から、何から何まで全部コントロールして」
後藤 「あらためて思いましたけど、世界中で行われてること、アメリカの穀物メジャーがアフリカでやってること、自分たちの音楽界が抱えている問題、社会が抱えている問題――どれも根本は似てますね」
中沢 「全部、同じ構造で問題が起こってますね」
後藤 「それは、いわゆる“土”みたいなところから、皆が離れすぎたってことですか?」
中沢 「“土”は動かないでしょ。これがやっぱり大事なとこで。リージョンとかローカルとか、地域性って、動かない“土”から出来上がってきたものが大事になってくる。音楽でいえば、ミュージシャンがリージョンとリージョンを横断していく、その間で何か発生するでしょ。これが音楽というものの面白さなんだと思うけど、リージョンがなくなっちゃうと、つまり地球が均質化しちゃうと、業界が先細ってしまう」
後藤 「それはすごく感じていて。たぶん今、もう一回音楽産業というか、ミュージシャンにとっての土を作り直さなければいけないと思うんです」
中沢 「そうそうそう」
後藤 「デビューしてすぐに思ったんです。自分がやってることが、なんて言ったらいいんですかね……、イマイチ伝わらないって言ったらアレなんですけど……」
中沢 「ポップだねえ(笑)」
後藤 「(笑)。だから、最初は種まきだと思ってやっていたんですね。海外のバンドと一緒にフェスをやったりすることや、様々な活動について。『ここで蒔いた種を、僕自身は収穫しないだろうけど』と思ってやってたんです。でも、どのジャンルもそうなんですけど、タコ壺化、クラスタって呼ばれる細分化されたグループに分かれて、そこだけにいればいいようになっていく。いろんな音楽を見ていて思うんですが、越境者が現れた時に、一番面白い現象が起きるんで、対流しなければ意味がないと思っていて。これがなくなってくると、音楽自体が文化として細っていくだろうなって」
中沢 「まさにそうなんだよね」
後藤 「だからまず僕は、横断しよう、越境しようと思ったんです。でも、種まきだと思っていたものの、最近、『これは種まきどころじゃないな』と気づいて。『土を入れ替えたいのかもしれない』って気持ちになったんです。それがイメージとして、農業にも通ずるんですけどね。僕らはツアー中、車で全国をまわるんですけれど、どこに行っても、どうしてこんなに農地が荒廃しているんだろうって。休耕田とかがたくさんあって」
中沢 「なるほどね。ミュージシャンにとっての“土”っていうのは、農業のように動かないでその土地が成長させてくれるものをジーっと待つのと同時に、リージョンを横断して越境していくこと。その両方の動きから出来てきてるんじゃないかな。一定の土地の中だけだと、おもしろい音楽って出ないんですよ。たとえば民謡って、元は移動して作られるものなんですね。移動してるときにすごくおもしろいものができるんですよ。『追分(※8)』の系統も、ものすごく旅するんですけど、その度におもしろくなっていった。そういう意味では、ワールドミュージックというものが出たとき、ものすごくおもしろいんだけど、こいつは危険だっていうのを両方感じたのね。今まで小泉文夫先生(※9)のレコードでしか聴けないような、アフリカ奥地の音楽とかが、すぐCDで手に入るようになって。僕なんか音楽が好きなんで、嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんだけど、『こいつはきっと危ないもんだな』って。均質化の道を進み、シャッフルされちゃう。本当の意味でリージョンを横断していく創造的なミュージシャンがいない限り、均質化しちゃうんじゃないかって感じたんです。実際、ある面でそうなっちゃったよね」
後藤 「そうですね。今はどこででも同じものを聴ける。今おっしゃったこと、最近すごく実感しますね」
中沢 「でもあらためて思ったけど、後藤君は『音楽を作るのは境界だ』という感覚がすごく強くあるんだね」
後藤 「はい。特にポップミュージック。ひとつの業みたいなものですけど、いわゆる資本主義や貨幣価値みたいなもの、都市というものとも関わらないといけないので。ただ、音楽を作るにあたっては、自分の中にある、外かもしれないですけど、どこにあるのかも分からない、プリミティブな洞窟、そういう“比喩としての子宮みたいな穴”に手を突っ込んで、何かを引きずり出して形にしている感覚があるんです。だからたぶん、音楽の中でもポップミュージックが農業に一番近いんじゃないかって思います」
中沢 「近いね、農業ってポップなんですよ。元々のポップミュージックというのは、知的じゃなく、人間の感覚のプリミティブでプライマルなものに直接触れちゃう音楽だから。だからなのか、今の若いミュージシャンを見ていると『そういう部分に自分がいつも触れてなくちゃいけない』と意識しようとしてる人たちが増えたよね。音楽ってものがどういうところから発してるのかっていうことを、直観的に分かってるのかなというのは感じますね」
後藤 「近しいフィーリングを持ってる人がたくさんいるな、っていうのは思いますね」
中沢 「あとほら、今は音楽の道具が良くなってるから、取り立てて音大に行かなくてもいいっていうね。機械で情報処理できるし。ちょっとやれば、それが出来るようになっているのも大きいと思うんですよね」
後藤 「あとやっぱり、いろんな情報に接続しやすくなったので、最短距離で辿り着けてるところがあるかもしれないです。読むべき本や聴くべき音楽に」
中沢 「そのとおり。僕らは無駄道がものすごく多くて。普通の人の四倍くらい生きてるのかなっていうくらい、いろんな無駄なことをしてきました。好奇心が強いから、こっち行かなきゃいけないのかなと思ったら、ワーッと行ってみて。無駄なことが多いんですよ。今みたいに情報が整理されていくと、羨ましいなと思う反面、でも自分がやった無駄なこともけっこう面白かったなっていうのは思いますね」
後藤 「たしかにバグみたいなものが起こりづらくなってますよね。『なんでこの本を読んで、こっちに興味が広がっちゃったんだ』みたいなことが。でもそういうバグこそ、何かを生んでくれてる感じがしますけどね。僕としては、もしかしたら音楽――ポップミュージックのことだけを考えて、自分の活動のことだけを考えてやっていくっていう道もあったかもしれないんですけど、いろんなところに興味の枝葉が伸びて、農業もふくめて、それが繋がっていく感覚があります。たとえるなら、中沢さんと内田さんが言っている“贈与”のように、返ってくるものがたくさんあっておもしろいですけどね」
(※6)マルクス
カール・ハインリヒ・マルクス。ドイツ出身の共産主義運動・労働運動の理論的指導者、経済学者、哲学者。『資本論』の著者
(※7)モンサント
アメリカのミズーリ州に本社を持つ多国籍バイオ化学メーカー。遺伝子組み換え作物の種の世界シェアは90%
(※8)追分
日本の民謡の一種。元々は信濃追分付近で歌われていた馬子唄が、関東以北の各地を中心に広がったとされている
(※9)小泉文夫
日本の民族音楽学者。日本を始め、世界中の民族音楽の調査や研究に従事。長年、テレビやラジオを通じて多くの民族音楽の紹介や啓蒙を行った


中沢新一(なかざわ・しんいち)
1950年、山梨県生まれ。明治大学野生の科学研究所所長。宗教から哲学、芸術から科学まで、あらゆる領域にしなやかな思考を展開する思想家であり人類学者。著書に『チベットのモーツァルト』(サントリー学芸賞)、『森のバロック』(読売文学賞)、『哲学の東北』(斎藤緑雨賞)、『フィロソフィア・ヤポニカ』(伊藤整文学賞)『カイエ・ソバージュ』全5巻(『対称性人類学』で小林秀雄賞)、『緑の資本論』、『アースダイバー』(桑原武夫学芸賞)、『芸術人類学』、『三位一体モデルTRINITY』、『ミクロコスモス』シリーズ、『狩猟と編み籠 対称性人類学Ⅱ』、『日本の大転換』など多数。