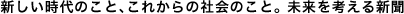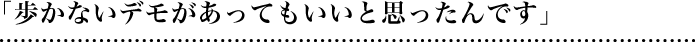後藤「僕、若手のロックミュージシャンの中でも、そういった問題に興味がある、ほとんど唯一に近い感じだったんで。でも、色んなことに興味を持って調べていくと、必ず坂本さんがいらっしゃるんですよね」
坂本「ハハハハ」
後藤「不思議なんですよ。原発のことなどを勉強し始めたころに、縄文時代への興味も始まって、調べていくとまた坂本さんがいて」
坂本「目の上のたんこぶだ(笑)」
後藤「そんなことないです。今も、『THE FUTURE TIMES』の取材先を探していて、友達と、“四国に面白いところがある。檮原(ゆすはら)っていうとこなんだけど、そこは自給自足でエネルギーを供給してて――”って話をして、よくよく調べていくと、“あっ、more Treesの森だ”みたいな(笑)」
坂本「moreTreesの手がついている。すみません(笑)」
後藤「いえいえ。あとは、原発の問題に興味が行く前に、日本の若いロックミュージシャンが、どうして、社会だったり、たとえば戦争だったり、そういったものにコミットしていかないのか不思議に思っていて。僕自身、歌詞に書くべきかどうか、発言していくべきか考えている時期があったんです。たまたま、坂本さんが表紙の雑誌を書店で見つけて。表紙に“反対しないと戦争はなくならない”って書いてあったんです。その記事を読んで、かなり勇気をもらいましたね」
坂本「悪い影響を及ぼしてるのかな。ハハハハ」
後藤「気が楽になりましたね。“ロックミュージシャンなんだから、気にしないで言えばいいんだ”って。そういうところから、だんだん原発問題などにも興味を持って、色々と踏み込んで、『THE FUTURE TIMES』を発行することにも至ったんです」
坂本「元々ロックミュージシャンなどは、普通の人よりも早く、そういうことが気になって、しかも社会に対し意見を言う人たちだったはずだから。60年代、70年代ってのはそうですよね。そういう伝統は欧米では、まだ減ってなくて。もちろん、そういう社会的発言をするのはクールじゃないみたいな世代もいますけど。でも、そういう伝統はまだ根付いてます」
後藤「そうですね」
坂本「日本は、民主主義自体も占領軍によって上からポンとこうもらっちゃったもの。ロックもやっぱり輸入品っていうことで、根付いてないのかな。今、根付く過程の中にいるのかなって感じもします」
後藤「そうですね」
坂本「そういうものが根付いていくって、たぶん時間がかかるんだと思うんです。2011年に、このような悲劇が日本にあったんですけど、これを大きなきっかけにして、別にロックミュージシャンに関わらず、誰でも自由に自分の意見は言いたいことは言える社会になったほうがいいと思います」
後藤「そうですよね。僕らの世代って、あんまり社会とコミットしないのが、クールというか、良しとしてきた時代で」
坂本「なんなんだろうね、その空気ってのは?」
後藤「なんでしょうね。だからデモにし対しても、ちょっと冷めた目で見てる人とか多いんです」
坂本「そうでしょうね。わかりますけど」
後藤「僕も最初はそうだったんです。だけど、だんだんと、“やっぱり、あれは行かなきゃいけないよ”って。デモも色々な形態のものがあって、方法については常に考えて行くことが必要だとは思いますけど」
坂本「そうですね。色々あっていいんじゃないかと思うんだけど、たとえば今回の原発事故を受けてのデモだとしたら、一番被害を受けている福島のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、ちゃんと簡単に入れるようなデモってなかなかないでしょ? やっぱり、一番困ってる人たちが、自分たちの意見を言いやすいようなデモや集会というのが、少ないような気がしてるんです」
後藤「そうですね。あと、事故からすぐの時に思ったんですけど、僕らを含めて若い世代が、割と“原発はやっぱりないとダメなんじゃないか”みたいな、ものすごい固定概念っていうか、凝り固まった思想みたいなものを、いつの間にか植え付けられちゃってるのが、ちょっと怖いなって思っていて」

坂本「それは、ありますね。だけど、片や世界に目を転じると、昨年は春からジャスミン革命や、ツイッターやフェイスブックなどのITを駆使した、非暴力の革命が起こった。本当に崩れそうもなかった、何十年も続いた体制をガラガラと崩せたり、その余波が今も中東で続いてるわけです。NYから始まったオキュパイ・ウォールストリートも、世界中に波及してますよね。あとは、たとえば福島の事故を受けて、事故のなかったドイツで、あっという間に数十万人規模のデモが起き、脱原発を決めちゃったり。ちゃんと発言するし、動きも早いですよね。それに比べて日本は当事国なのに、ちょっと元気がないというか」
後藤「そうなんですよね」
坂本「以前に比べれば、100人くらいでデモしてたのが、何万人も集まるようになったという、大変な違いはあるんですけどね。やっぱり、ズルズルと、既得権者に引っ張られているような。まあ、あの人達、エリートだし、頭もよくてお金もあるし、なかなか手強いですけどね」
後藤「うーん、そうですね」
坂本「簡単には引き下がらないでしょう。そんな事はわかってますけど。もうちょっと元気出したほうがいいんじゃないかと思いますけどね」
後藤「社会全体に他罰的な雰囲気があると感じてるんですけど、叩くのが好きというか。とにかく異端者を見つけ叩く。それがちょっと、個人的には窮屈に感じていて。それゆえに発言しにくい感じもあるんじゃないですかね」
坂本「なるほどね」
後藤「だから、『THE FUTURE TIMES』では、自分達も含めた若い世代が、社会に対して大きな声を上げるというよりは、日々の選択の質を高めるというか、そういう意味で社会にコミットしていくことも提案したいんです。たとえば、良い物を買うとか、良いエネルギーを選ぶといったことでしか、社会は変わらないと思うので」
坂本「そうですね、消費者は毎日、投票をしてるわけですから。つまり、AとBという商品があったら、Aを買ってBを買わないというのは、ひとつの選択、投票行為であって、その背景に、Aという商品を作っている会社は、このくらいエコフレンドリーだとか、エコマイレージ、CO2をどのくらい出していないとか、原発推進じゃないとか、色んなことを調べて商品を買うというエコ消費者、グリーンコンシューマーが世界的に多くなっている。そしてこれは、企業にとって注意しなくてはいけない問題になってきてるんです。会社の方針で商品が売れたり売れなくなったり、選ばれてしまうわけですから。もっと環境への負荷は下げようとか、原発で作られる電気ではなく自分のところで発電しようなどといった気運にも繋がっていくはずです。だから、消費者ってのは一番強いんですよ」
後藤「そうですよね」
坂本「うん。一番声を持ってる」
後藤「まさに、そういう部分に働きかけたいっていう趣旨で、この新聞を始めたんです。つまり、歩かないデモがあってもいいんじゃないかと思ったんですね。最初の発想はそこです。あと、ミュージシャンの端くれとして、音楽の歴史をひも解いていくと、やっぱりミュージシャンがニュースペーパーの役割をしていた時代も昔はあって。それもひとつのヒントだったんです。“じゃあ、俺もう1回新聞屋になってみようかな。音楽家として”って」
坂本「確かにミュージシャンが、新聞屋の役割を担ってましたよね。独裁的な政府があるとして、新聞では反対意見とかは掲載できない。もちろん『THE FUTURE TIMES』には、反対意見ではなく、積極的なポジティブな意見や情報が載ってますけど。たとえば、この間のエジプトや、今のシリアみたいに、すごい独裁的な政治下で、新聞で反対意見を書けない場合、みんながやるのは替え歌だったりする。文字で残すと証拠になっちゃうので。歌は空気の振動ですから。でも、歌が文字よりも、バーッと広がるということは、たくさんある。歌って、そういう面もありますよね」
後藤「そうですよね」
坂本「メッセージを乗せていく媒体ですからね。でも、ためらう部分があるでしょ?」
後藤「ありますね。どう表現すればいいかとか。それによくあるのが、清志郎さんを例に出して、僕たち若いミュージシャンを叩いてくる人達っているんです。“お前らロックとか言って、なんで反原発の歌を歌わないんだ”みたいな」
坂本「そっちから叩くんですか」
後藤「そうなんですよ。“そういう歌を聴いて過ごしてきた、あなた達が作ってきたのがこの社会なんじゃないですか?”って思うんですけどね。だけど、僕も一曲作ったんです。かなり抽象的な曲にはなってしまったんですけどね。僕は僕のやり方でやれたらなと思って。ダンスミュージックを意識して作って、歌詞を意識せずに踊って、気付いたら、“すごいこと歌ってんだ”って曲にしたいなと思ったんです」
坂本「なるほど。僕もよく聞かれるんですけど、環境問題に関心を持って長いじゃないですか。すると、“作る音楽は変わりませんか?”って言われるんですけど、変わんないですね。エコな音楽になってこないですからね」
後藤「そうですね」
坂本「リラクゼーション的な音楽に変わっちゃうのはね。まさか、アジカンがそうなることはないでしょうけど。自分の音楽を変える必要はないと思いますね」


坂本龍一(さかもと・りゅういち)
1952年東京生まれ。78年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、細野晴臣、高橋幸宏と『YMO』を結成。84年、自ら出演し音楽を担当した『戦場のメリークリスマス』で英国アカデミー賞受賞。映画『ラストエンペラー』の音楽でアカデミー賞、グラミー賞他受賞。90年代から、環境・平和問題に言及することも多く、論考集『非戦』を監修。自然エネルギー利用促進を提唱するアーティストの団体『artists'power』を創始するなど、活動は多岐にわたる。