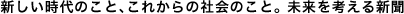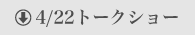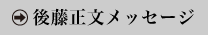佐藤「新聞やテレビからの情報では、なかなか実感が湧きづらいですよね。現地に何度も足を運んでいる自分ですら、あの光景は夢だったのではないかと思うくらいです。2万人弱の人が亡くなられたと“数字”で言われても、逆にひとつひとつの死のリアリティが希薄になってしまう。僕は母を探して何日も避難所巡りをしていたのですが、圧倒的な破壊の光景を前に、『もう生きていないんじゃないか』と思うようになり、徐々に安置所に足を運ぶようになったんですね。体育館に400、500もの遺体が安置されている。その一体一体の遺体を、『もしかしたら母なんじゃないか』と思いながら見て行くわけです。目の前に横たわる数百というその遺体の数がまず想像できないですし、その個々の死の裏にある遺族の思いを想像すると、何十倍、何百倍もの痛み、悲しみがあるわけじゃないですか。僕の母の遺体は結局、一ヵ月後に川の上流で瓦礫の下から見つかったのですが、そのたったひとつの痛みですら受け止めきれずに残っている。被災地にはそういった数え切れないほどの悲しみが残っていて、ニュースではなかなか伝わりません。物理的に大切な人や故郷、家や職場が無くなってしまっただけではなく、それらを大切に思う全ての人たちの心の内に、大きな喪失感が残っています」
安田「佐藤の一家もそうですし、去年からお世話になっている地元の消防団の方がいるのですが、街の方々を逃がしている間にお子さんと奥様が流されてしまいました。1年経って今年の3月11日に『自分自身の心の中の秒針は1秒も動いてない』とおっしゃったんですね。今日が何日で何曜日か、人に言われないとまったくわからない、と。去年の5、6月頃から『復興に向けてがんばろう』という報道やイベントが溢れてきて、もちろんそれらにも大切な意義はあるのですが、その陰にはまだまだ立ち上がれない人々のたくさんの沈黙があると、発信する私たちも自覚しないといけないと思います。どういう希望も、どういう復興も、死を悼む時間を抜きにしては、脆いものになってしまうなと感じます」
後藤「代弁できないんですよね、それぞれの悲しみは。どれだけ想像してもその人になることはできないですから」

渋谷「私もそう感じて悶々としていた時期があって。放射能、原発事故による被災者の苦悩を代弁することはできない。でも想像することはできるかもしれない。だから原発のそばに行って、その目に見えない恐怖を、福島で起こったことを、体で、あるいは心で、目いっぱい感じてやろうと思ったんですね。なぜこんなことになってしまったのか、自分に問いを突き付けたかった。でもやっぱり見えないものは見えないし、恐怖や無力感とか、自分の中で言葉にできない感情が渦巻いていました。目の前の光景に現実感が持てなくて。そんなとき、ドラえもんのぬいぐるみが動物の死骸の側にあって、どうにも気になって2、3枚シャッターを切ったんです。そのあと『なんで気になったんだろう?』と思ったら、ハッと思い出して。そのときは4月の始めだったんですけども、私の長男が小学校に入学したばかりで、嫁さんの両親が送ってくれた電報についてきたぬいぐるみと同じだったんですね。そういう小さなことがきっかけで、目の前の非日常と自分の日常がリンクして、ダムが決壊するように色々な想像が浮かんだんです。ここに自分の息子のような子供がいたこと、子供の成長を喜ぶ家族がいたこと。そしてその故郷が容易に帰れない土地になってしまった悔しさ。その感覚だけはほんの少し掴めたというか。すべては到底わからないんですが…」

後藤「詞を書いたり、発信する側に立って思うのは、いま渋谷さんがおっしゃったぬいぐるみのような“ディテールを切っていく作業をしない”こと。たとえば“被災地”という言葉にまとめてイメージをひとつに集約しないこと。そこには想像できないような多様な現実が存在します。大きなメディアは集約して一般化しがちですし、僕たちもひとつにイメージをまとめてしまうことが多いんですけど、言葉はひとつの事柄を抽象化するためにあるので、目を向けないように閉じ込めてしまう危険性がある。だから、フォトジャーナリストの方々がこうやって多面的に語ってくれることで、伝わるものがあるんですよね」
佐藤「東京と岩手を行き来する生活が続いているのですが、東京に戻ってくるとまったく平穏で、被災地での出来事が『まるで夢の中のようだ』と感じたんですね。街を歩きながら、自分が置いていかれたような孤独をずっと感じていました。1年以上経って、ニュースも流れなくなって、みんな震災のことなんか忘れているのかな、もう関心ないんだろうなと、少し感じてました。でも今回の写真展に来てくださった方々の表情を見ていて、『無関心だったわけじゃない。みんな、何もできないでいる自分に対する罪悪感や、あまりにも自分が小さすぎるという無力感を抱えていて、それをどこにも表現できなかったり、誰かと話したりすることができてなかっただけなんだ』と感じました。また『地震は起きてしまったことなので、これをなんとか糧にしていきたい』とも会場で声をかけられました」
後藤「嬉しいですよね。あと安田さんは、現地で『もっと写真を撮っておいてほしかった』と言われたとおっしゃっていましたよね?」
安田「去年の3月に『何か役に立てるかもしれない』と現地に入ったものの、あまりの状況に圧倒され、戸惑いながらただ日々が過ぎてしまって、3月当時の写真がほとんどないんです。でも最近になって地元の方が『もし3月にあなたたちカメラマンと会っていたら、撮るんじゃない!と怒鳴っていたかもしれない。でも今となっては、撮っておいてほしかった』というようなことをおっしゃっていたんですね。 陸前高田の中でも、どこまで津波が到達して、どれくらい瓦礫があって、どれほどの被害があってというのが、時間が経つほどに曖昧になってしまっている部分があるんですね。実は明治の大津波のときに建てた、津波の到達点を知らせる石碑が市内にはたくさん残っています。今回の津波の到達点は、ほとんどその石碑の位置と一致しているんです。にも関わらず、同じ悲しみが繰り返されてしまった。何を忘れてはいけないのか、何を次の世代に残さなければならないのか、考えることが大切です。それは現地の方々の課題でもありますし、撮る私たちの課題でもあると思います」
後藤「そのあたりどうですか、震災を経て。みなさんは“フォトジャーナリスト”という肩書きがあるわけですけれども、残すものへの意識というか、あらためて言葉にできたりしますか」
佐藤「僕自身はこの二人より全然フォトジャーナリストとしての経験が浅いのですが、僕が伝えたいのは後藤さんがおっしゃったように“ディテール”なんですね。僕が今回の震災で経験して感じたことは正解でも不正解でもない、僕という個人が経験したひとつの事実に過ぎないのですが、それを伝えることで、みなが震災について考える際の参考にしてくれたらという思いはあります。ディテールを伝える表現手段として、写真はすごく効果的なものだとは思うし、そのひとつの写真に写った光景から、見た人が自分なりの言葉を紡いでいただけたら嬉しいです。」
後藤「佐藤さん、文章も素晴らしいですよね。『ファインダー越しの3.11』という著書を三人で出版されて、読ませていただいたんですけれど、佐藤さんの文章、ぐっと来ましたね」
佐藤「ありがとうございます」
後藤「渋谷さんはどうですか?」
渋谷「そうですね…写真展にこれだけの方がいらっしゃるのは、初めての体験なんですね。しかも若い人がほとんどで、素直に嬉しいんですけど、会場で観察していると出たり入ったりしている方がけっこういたんですね。感想ノートを読ませてもらったら、『逃げたくなった、でももう一回入って見なきゃいけないと思った』とあって。そういう葛藤は、僕が被災地に入って感じる葛藤と似ていると思ったんです。当然ですけど、写真をパシャパシャ撮れたわけじゃない。できることなら撮りたくない。1日も早く帰りたい、ここはいる場所じゃない。正直、そんなふうに感じながら、被災地で取材していました。でも自分にしかできないことがあるんじゃないか、向き合わなきゃいけないことがあるんじゃないか、と自問して。自分の中の感情をごまかしたり、感情に蓋をしたり、見て見ぬふりをしたり。そうした葛藤を持つことは悪いことじゃないと思うんですけど…そんな色々な思いを凝縮した1枚が撮れたら、被災地に行けなかった人にも少しでも何か感じてもらえるんじゃないか、と。写真の力というのは、僕ができることはせいぜい半分で、あとの半分は写真を見てくれた人の想像力で補われて、ひとつの伝える仕事が完結するんです。写真を見て何か感じているお客さんを見て、何かが届けられたのかなぁと感じました」
後藤「はい。まだ聞きたいこともあるのですが、そろそろ時間になりました。最後のテーマとしては、『TFT』にちなんで、これからの未来について一言を」

佐藤「今日、会場にみなさんが入ってくるのを見てたんです。ひとりひとり、その人自身が生きてく中での幸せって色々なものがあるんですよね。決してひとつのことで成り立っているわけではなくて、愛する人がいて、家族や友人がいて、職場や趣味もあって…。ただ、そういうものは確かなものではなくて、いつどの瞬間になくなってもおかしくない。大切なものがあるということは、同時にいつかそれを失うかもしれないという悲しみも共にあると思うのですが、なかなかそれには気づかない。いわゆる被災地と呼ばれる場所にはそういった痛みが溢れている。父も、彼にとっては最愛の妻を失った。そういう経験を経た父は、震災直後の記憶が曖昧なんですよね。辛い記憶がだんだん思い出せなくなっている。忘れることで前に進める記憶というものも確かにあるとは思いますが、逆に絶対に忘れてはいけないものもある。それはなんだろう、と考えると、それは大切なものがあるゆえの痛み、愛する者がいるゆえの痛みなんですよね。表裏一体だなと思って。その痛みに蓋をすると、その逆にある喜びとか人を愛する気持ちにも蓋をしてしまう。そこからは目を背けてはいけない。大切な痛みを見つめること、それが未来に繋がるのではないか。そんなことをこれからも『TFT』でもっともっと多くの人に伝えたいと思います」
後藤「ぜひまたこれからも参加してもらえたら嬉しいです。続きまして、安田さん…」
安田「まだまだ1年で、人が何かから立ち直ったり、完全に前向きに歩むにはあまりにも短い期間です。現地の方々に声をかけるなら『早く復興してね』ではなく、『自分のペースを大切にね』と言葉をかけたいです。でも言葉というものは態度が伴わないと伝わらなくて、その私たちの態度ってどういうものなのかなと考えると、やっぱり通い続けて発信し続けることだと思います。私たちは写真という媒体を選んでいますが、写真って撮るだけでは未完成なんですよね。それを受け取ってくださるみなさん一人一人の心の中に受け入れられて初めて、ひとつのかたちになると思います。何かこうみなさんにあてた、言葉ではない手紙の1枚1枚だと思うんです。でもその手紙も『早く読んでね』と押しつけたくなくて、今日みなさんも何枚か写真を見てくださったと思うんですが、心の中になんとなく持ち帰っていただいて、自分のペースで読み解いていただけるものであってほしいです。そんな写真が心の中に、いつか花開く種のように残って、たとえばそれが明日かもしれないし、1年後、5年後でも、そのなんとなく種として残っているものが、いつか一歩を踏み出すきっかけになるといいなと思います。そんな気持ちで写真を撮っています。なんか、まとまらなくてごめんなさい」
後藤「いえいえ。僕もミュージシャンという立場で東北の沿岸部に何回か行かせてもらいましたけれど、たとえば『復興しましょう』とは言えないんです。そんな無神経な、って思うんですよ。“歌ってくれ”という空気になってきたら、おずおずと出て行って『歌いましょうか?』みたいな、そういう感じでもいいのかなという気がするんですよね。そこにいるだけというか、寄り添うというか。完全に現地のことを忘れて、遠い所で『復興!復興!』って言ってるのが、自分としては一番無神経に感じます。南相馬に取材に行ったら『2012年が復興元年だ』って言うんですよ。1年間、まったくそんなこと考えられなかったって。『ここから手探りで始まり ます。やっとスタートラインです』っていうところなのに、マスメディアの震災報道は終わっていく。なので、ぜひぜひこれからも、みなさんに『TFT』で伝えていただきたいなと思います。最後に渋谷さん、お願いします…」
渋谷「昨日の後藤さんのライブを聴いてたんですけど、去年あんなことがあって、それでも後藤さんはどうして歌うんだろうと考えてたんです。自分自身、写真を撮ってると、決して楽じゃないし、人をどちらかというと傷つけたり、自分も傷ついたりするのに、どうしてやるのかなと考えたんです。結局、人間というのは本来的に残酷で、罪深くて、過ちを犯してしまう動物なんじゃないかと思うんです。これまでの色々な取材経験から私はそういう人間観を持ってしまっていて。それがエスカレートすると戦争だったり、飢餓であったり、そういうことを引き起こしてしまう。なんで人はそういうことをしてしまうんだろうと思う反面、だからこそ、そういう人間を肯定したい気持ちもある。だから未来を想像した時に、少しでも人間が優しい存在であったり、あるいは社会が他者に対して優しい、そういう成熟とか進歩があって、生きててよかったなぁと思える時代が来るんじゃないかなと。そういう時代を自分の子供たちに渡すために、自分は生きていきたいなと」
後藤「渋谷さん、昨日の話(注.このトークショーはイベント2日目)、もう一回してもらってもいいですか? 僕が『今年の3.11以降、バーっと流れていたニュースがなくなってしまった。むしろ、2012年の3月12日以降の話が大事なんじゃないか』という話をした時の…」
渋谷「ああ、『2011年の3月10日以前が大事だ』という話ですね。未来を考える上でやはり過去をもう一度考えなければならないと、僕はこの1年で思うようになったんですね。東北は津波を何度も経験していて、たとえば90代の方から昭和8年の津波の経験を聞いたんですね。その経験を教訓にできた所とできなかった所があった。あるいは原発事故のことにしても、3月11日に急に問題が起こったのではなくて、それ以前からあった。原発54基は昨日今日できたわけではなくて、1960年代から続いてきて、もっと言うとその要因は戦前までさかのぼるのです。なぜこういうことになったのかという歴史的な経緯も含めて、伝えていかないと未来に繋がらない」

後藤「過去から学ぶこともあまりにも多いですもんね。『THE FUTURE TIMES』と言って未来のことだけ考えていると、ほんとただの能天気な人になってしまうんですよね(笑)。自分たちが歩んできた道を振り返りながら、——そういうときにこういう写真が残っているというのが僕は凄く重要だと思うんで。皆さんが覗いているファインダーというのは、僕たちの代わりに覗いてくれているんだと思っているんですけど、これからもそういう形で記憶を残していただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました」
渋谷・佐藤・安田「ありがとうございました」


渋谷敦志(しぶや・あつし)
1975年、大阪府生まれ。高校生のときベトナム戦争の写真を見てフォトジャーナリストを志す。大学在学中にブラジルに渡り、法律事務所で研修しながら写真を本格的に撮り始める。London College of Printing(現ロンドン芸術大学)でフォトジャーナリズムを学ぶ。現在は東京を拠点に、世界の紛争や貧困、災害の現場で生きる人間の姿を写真で伝えている。1999年MSFフォトジャーナリスト賞、2000年日本写真家協会展金賞、2002年コニカミノルタフォトプレミオ、2005年視点賞・第30回記念特別賞など受賞。アジアプレス所属

佐藤慧(さとう・けい)
1982年岩手県生まれ。
studio AFTERMODE所属。大学時代は音楽を専攻。世界を旅する中でその不条理に気付く。2007年にアメリカのNGOに渡り研修を受け、その後南部アフリカ、中米などで地域開発の任務につく。2009年にはザンビア共和国にて学校建設のプロジェクトに携わる。
2010年studio AFTERMODEに入社、ジャーナリストとしてアフリカを中心に取材を始める。東日本大震災により両親の住んでいた街、陸前高田市が壊滅、復興支援団体「みんつな」を立ち上げ支援に関わりながら取材を続ける。写真と文章を駆使し、人間の可能性、命の価値を伝え続けている。2011年世界ピースアートコンクール入賞。東京都在住。

安田菜津紀(やすだ・なつき)
studio AFTERMODE 所属
フォトジャーナリスト
2003年8月、「国境なき子どもたち」の友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。2006年、写真と出会ったことを機に、カンボジアを中心に各地の取材を始める。現在、東南アジアの貧困問題や、中東の難民問題、アフリカのエイズ孤児などを中心に取材を進める。2009年、日本ドキュメンタリー写真ユースコンテストにて大賞受賞。共著に『アジア×カメラ 「正解」のない旅へ』(第三書館)など。上智大学卒。