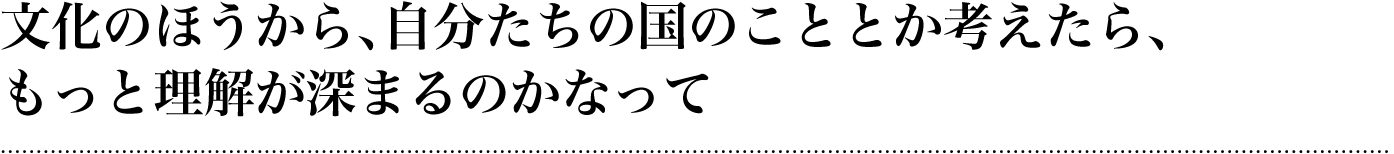後藤「若い子たちは文楽をどう思っているんですかね。パっと見た感じは、やっぱり年配の方が客席には多いですよね」
清志郎「そうですね。若い方はずいぶん少ないです。正直なところ、僕はまだそんなに小さい子に見てもらわなくてもいいと思います。なんでしょう、これを小学生ぐらいで “おもしろい” とか言い出したら、もうちょっとおもしろいものあるだろうとか思うんですけどね(笑)」
後藤「確かに(笑)」
清志郎「その時代の新しいものをもっと観て、それで、もうそろそろ刺激よりも、その場で静かに観られるようなもの、ゆっくり落ち着いて見られるようなものを “何かないかな” と辿ってきて、最後に辿り着くのが文楽であってほしいなと思っています。世の中に文楽があるということだけは知っておいていただきたいですけど」
後藤「でも、感じるところはありますよね、若い世代でも」
清志郎「最初は、人形の美しさや着物の色彩なんかは若い人でも十分何か感じるところがあると思います。今は、洋服でこんな色の合わせ方をしてきている人なんか、いないですからね。ピンクと水色を、重ねていたり、オレンジと青が一緒になっていたりとか。不思議な衣裳を着ているし、本当に、色だけで、昔の色彩の凄さといいますか、そういうものを楽しめるし。きっと何かしら、観ていただいたら光るところがあるはずだと」
後藤「同世代には特に勧めたいですけどね。おもしろいですよって」
清志郎「そうですね、そのぐらいの方になってくると、僕もお話がしやすいというか。手放しに “おもしろいから来い” とはね、ちょっと言えないんですけれども、きっと期待を裏切らないですよね。出演者も、それぞれの方がやっぱりがっちり修行をしているので。それぞれ説得力があって、全体的にはすごく安心して見ていただけるお芝居じゃないかと思います」

後藤「あと、今日のお客さんたちって、多分60代の方がたくさんいらっしゃったと思うんですけど、その世代がガクっといなくなる時がいつか来るじゃないですか」
清志郎「でもその時には、今の30代が60才になっている」
後藤「そのときに僕らの世代がちゃんと文楽と繋がっているといいなとは思います。それほど、僕らは伝統芸能と繋がっていないように思うんです。でも、そういう流れ、伝統的な日本の文化に接続しようっていう動きがきっと起きてくるんじゃないかという気がしています」
清志郎「そうなって欲しいです。僕の偏見ですけれど、日本を出て海外や陸続きの国に行くと、国境が接しているから結局、競うのは “人” や “文化” という意識が高いのか、自国の文化をすごく大事にしている気がしているんですよね。でも、日本は島国で、いつも海の向こうに思いを馳せてきたのか、外のものを取り込んで、良くしてまた世界に発信して跳ね返していく。それが日本の素晴らしさであると考えると、なかなか日本国内の特有のものに目を向けないというのが、日本人の良さなのか悪さなのかと考えてしまうんですけれども」
後藤「なるほど」
清志郎「ただ、海外に出た時に、自国の文化に何があるのかというのを語れる人が何人いるのかと思うと、文楽や歌舞伎とかも知っておいてもらえると対等に話ができるんじゃないかなと思うんです。それは武器ですからね、自国の文化をちゃんと説明できるというのは。なかなか海外の人と話す機会がないとは思うんですけれども」

後藤「でもこれは、どうやってみんなにおもしろさを伝えようかというのはちょっとね、考えてしまいますね。僕も分かっていない側の代表みたいなものなので(笑)」
清志郎「いやでも、だからいいんじゃないですか。専門家の方が難しく “あそこがおもしろいから、あそこを見なさい” みたいなことじゃなくて、分からなくても “観たら何かおもしろいところがある” というのを漠然と書いていただいたほうが、きっと安心してみんな来られるんじゃないかなと思うんですけどね。分からないのが普通と思って来てくれはったら」
後藤「そこがなんて言うんですかね、恥も外聞もないというか、堂々と “僕知らないんで” って入っていくのも違う気がして。 “あまり詳しく知らないんですけど、これから勉強しながら楽しみます”みたいな気持ちがあって。 “チケット代を払ってんだから楽しませろよ” という態度ではなくて、想像力を使って参加するというか。観客として自分から中に入っていくイメージというか」
清志郎「嬉しいです。確かに、聞いてくださる方が自分で掴んでくれないと、入ってこない部分が多いかもしれませんね。 “ここはこうです、あそこはこうです” って、 “一緒に盛り上がりましょう” っていうような感じじゃなくて、ひとつ幕があって、僕らは教わった通りを淡々と演じる、そしてそれを淡々と受け取ってもらっているというような」
後藤「きっと、昔はこれを普通に観て楽しんだんでしょうけど、そんな町人の楽しみの中にも “粋というのはどういうのか” という物差しがあったんじゃないのかなとも想像するんです。僕は相撲が好きで観に行くんですけど、やっぱイケてるおじいさんとかは、お茶屋さんがビールや弁当を持ってきてくれると、ポチ袋みたいなものをピッと出すわけなんですよ。格好いいと思って。大人の嗜みみたいな。あれが粋で、そういう文化がやっぱりあるんだなって」
清志郎「そうですよね、昔はそういうのがあったんですね。ほんまに、丁稚奉公に入ったら、まず落語を聞かして、いろいろなルール、説明しづらい、大人の?ルールも含めたものを全部それで教えたという話もあるぐらいですから。きっとそういうのがあるんでしょうね。心付けを渡す話とか、いろいろ」
後藤「落語ならば、その笑い話の中から、ちゃんとユーモアとして知性を汲み取れということなんでしょうかね」
清志郎「そうでしょうね。お相撲観たり、歌舞伎観たり、文楽観たり、無駄なようで、きっと身につくものがあるんでしょうね」
後藤「一見、無駄に思うようなものを楽しむ心のゆとりというか。ギスギスしていないというか、そういうのが昔は、今よりもあったのかもしれないですね」
清志郎「確かに、後藤さんがおっしゃるように、(伝統文化に注目が集まるような時代が)来るといいですね。今ちょうど一番失われている、波が一番引いた状態かもしれませんから」
後藤「そうなんですよ。愛国とナショナル・アイデンティティみたいな話は、みんな大好きでよくするわりに、文化の話ってあまりしないじゃないですか。文化のほうから、自分たちの国のこととか考えたら、もっと理解が深まるのかなって」
清志郎「確かに、自分の国らしいものって、考えたら、今はここにいるからやっぱり文化的なものしか全然浮かばへんのですけど、他に何があるのかって思いますけど、意外と “文化” って言わないですね」
後藤「相撲とかもそうで、ものすごいみんな単なる “スポーツ” にしたがるんですけど、あれってよく説明のつかないところがあるからおもしろいと思うんです。武道でもあるし、興行でもある。芸能みたいな側面もある。 “スポーツなんだから、お前ら全部ガチンコでやれよ” って糾弾するのは、全然、粋じゃないなと思うんですよね。欧米の価値観が勝ち過ぎているというか 。“白黒つけろ” みたいな…。すみません、全然関係ない話(笑)。話を戻します。文楽も、そういう意味では観どころ聴きどころがありすぎると、最初に来て思いましたけどね。総合的な、複雑な表現なんだなと」
清志郎「突っ込みどころも満載ですしね(笑)」
後藤「はい。『文楽かんげき日誌』に寄稿させてもらったんですけれど、『本朝廿四孝(※5)』を観たときに、クライマックスで狐が現れるシーンがあったんですけど、橋の下の小さな窓がカパッと開いて出てきた狐がショボくて(笑)。あれ、なんとかならないですか」

清志郎「僕もなんとかならんかなと思うことがあります(笑)」
後藤「だって、他のところは完璧で(笑)。八重垣姫(※6)が行ったり来たりして盛り上がって、クライマックスってなって、その後でパカってショボい狐が出てきて、 “ええっ?”という(笑)。そういうアンバランスなところも、僕はちょっと好きになりましたけど」
清志郎「なんでも合理的というか、全部理屈通りにやっていないところも、昔のおもしろさかもしれませんね」
後藤「ただ、なんと言うか、いつしか言葉は昔の言葉になって、どうしても距離が開いてくるなかで、どんどん観に行く側が敷居の高いものだと思い込んだのかもしれないなと思いました。例えば、今日の『曾 根崎心中』とかを観ると、普通に恋物語なのになぁとか」
清志郎「根本的な部分は、ずっと変わらない普遍的なテーマですものね。恋愛とか親子の情愛とか、400年前から、 “人間って同じ事ばかりやっているんだな” というようなことばかりが題材になっていますから。単純に考えて聞いてもらったら、それだけの話しですけど、ね。なんか難しく思われがちですよね」
後藤「でも、やっぱり長い年月を残ってきたものなので、ありがたみも感じますけどね。300年生き抜いているという」


鶴澤清志郎(つるざわ・せいしろう)
1974年長野県生まれ。1992年に国立文楽劇場第15期研修生となり、1994年に鶴澤清治に入門。清志郎と名乗る。同年6月、国立文楽劇場で初舞台。
(※5)本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)
時代物の浄瑠璃義太夫節。近松半二、三好松洛、竹田因幡、竹田小出、竹田平七、竹本三郎平衛による合作。初演は1766年。武田・上杉両家の争いを骨組みにした複雑な構成の作品。
(※6)八重垣姫
上杉謙信の娘。花作りの蓑作として現れた、死んだはずの許嫁・武田勝頼を追手から守るために、奥庭にある兜を盗み出し、兜を守護する霊狐に導かれて諏訪湖を渡る。