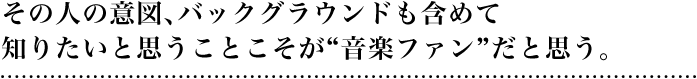1980年からスタートしたクラブイベント『ロンドンナイト』を現在も主宰、ロックDJの先駆け的存在でもある音楽評論家の大貫憲章。彼が持つ膨大な数のレコードや、そもそも“音楽を聴く”ということへの根本的な姿勢について、30年以上に渡りロックDJを続ける情熱の由縁を探った。
――まずは、大貫さんが音楽と出会った頃のお話から……。
大貫憲章 「小学校の頃から、『シャボン玉ホリデー(※1)』や『ザ・ヒットパレード(※2)』で、坂本九やクレイジーキャッツが歌詞を日本語に変えて洋楽をカヴァーしていて。元々は外国の曲だったんだなって思ったり。その後に受けたエレキの衝撃は凄くて。中学校の1、2年ごろには、既に『ミュージックライフ(※3)』っていう雑誌があったので、そういうのを読みながら、知識を増やしてレコードを買ったり。あの頃はラジオもおもしろい番組がいっぱいあったのでそれを聴いて。さすがにテレビでは洋楽をそのまま流したりはしていなかったですけどね。でも、1966年にビートルズが日本へやってきて、そのときついに特番なんかが組まれました。彼らが飛行機で日本に到着したのは深夜でしたけど、日本テレビが生中継をしていて。法被(はっぴ)を着て羽田空港に降り立って、パトカーに先導されてヒルトンホテルまで向かう映像を、食い入るように見ていましたね」
――生でそれをご覧になっていた、と。

大貫憲章 「そう。そういうところからも、洋楽に対して特別な感情を抱かざるを得なくて。ラジオでいうと、『9500万人のポピュラーリクエスト(※4)』の影響が大きいです。当時の人口が9500万人だったみたいで。カウントダウン形式で新譜の紹介もあってっていう番組を当時は漠然と聞いていたんですけれども。当時は、レコード会社が持っているレーベルからのチョイスで曲がかかるので、ヨーロッパの楽曲がよくかかっていたんですよ。アメリカを経由しないで、直で日本にヨーロッパのものが紹介されるっていう。『サンレモ音楽祭(※5)』、今でいう『ユーロビジョン・ソング・コンテスト(※6)』の前身が50年代に生まれて、それが60年代になって盛り上がって、ヒット曲が出てきたんですよね。ボビー・ソロ(※7)とか。そうすると日本でもシングル盤になるっていう。そうやって、アメリカ一辺倒じゃなかったのが、自分にとっては良かったのかなとは思います」
――今とは流行り方が随分と異なるんですね。
大貫憲章 「映画音楽に関してもそう。それ自体がシングルになって売られるっていう形は、70年代以降にはなくなったと思うんですよね。それまでは、『白い恋人たち(※8)』——グルノーブルの冬季オリンピックの曲ですけど、ああいう楽団の曲も、“BGM”ではなく普通にヒット曲として流れていたので。音楽のジャンルに対する偏見がなくなんでも平等に聴けたのは、あの時代の特殊な一面だとも言えるし……。それが幸せだったと思います」
後藤 「そうなんですね」
大貫憲章 「自分でDJをする時も、いろんなジャンルを流すと、特に外国のお客さんに“君のDJはユニークだ”って言っていただくんですよね。つまりそれは、他の人はDJをするとなればある程度同じジャンルを流すものだけれど、 “君のDJは80年代メインかと思えば60年代もかかるしジャパニーズも平気でかける、そんなDJは見たことない” という意味。そういえば、嘘か本当かわからないけれど、サンディエゴにクラブ持っているから回さないかって言われたこともありましたね。まあ、その後に連絡はなかったですけど(笑)」
――じゃあ、レコードも幅広いジャンルを持っていらっしゃるんですね。

大貫憲章 「はい、今でも昔のシングル盤、映画音楽とかを買いますね。特に、当時聴いていたものをよく買っている。『夜霧のしのび逢い(※9)』っていう、日本に住んでいるクロード・チアリさんの大ヒットした映画音楽とか、今でも状態が良ければ買いますし。アラン・ドロンが主演した“太陽シリーズ”の曲(※10)とかね。あとは、フランス人で最大のヒットだったサルヴァトール・アダモ(※11)、そういったものも購入してますね」
後藤 「どのくらいの数のレコードをお持ちなんですか?」
大貫憲章 「数で言うと、LPとシングル併せて3、4万枚だと思います。正確に数えたことは無いですけど(笑)。前はもっとあったんですけども、整理してね。大半が洋楽で、レコードの邦楽は一割あるかないかといったところでしょうか。CDになると洋邦の比率は7:3くらいですけどね。ただ、黒人音楽っていうか、ディスコのものはあんま無いですね。あとはヘヴィメタルの強力な奴は伊藤政則(※12)さんにお任せしているので(笑)。ほとんどがロックやポップスです。購入するのも、CDしか売ってない場合はCDを買いますけど、基本的にはレコードですね。DJで使うならレコードを探します。CDJは凄く進化してますけど、稀(まれ)にしか使わない」
――そんなレコードの魅力とは?
大貫憲章 「ひとつはこだわりです。ジャケットが付いていたほうがいいし。あとは、理屈じゃなくて愛着の部分がかなり大きい。こういう『The Future Times』のような新聞を手で触りたいっていうのと同じ。レコードをターンテーブルに置くっていう、ずっとやってきた一連の作業が大好きなんですよね。音が出るにはどちらでも一緒じゃんって言われるかもしれないですけど。まあ、不便なことも多いですよ。DJをしに行ったらターンテーブルがなかったこともあってね! そのときはお客さんに土下座して “俺、今日DJできないぶん踊りますから許してください”って言いましたけど(笑)」
後藤 「(笑)」
大貫憲章 「それ以降は、必ず現場にターンテーブルがあるかどうか確認するようになりました。それと、レコードはCDよりもノイズを拾うことが多いです。ターンテーブルを普段使わない主催者だと、アースを繋いでいないことがあるんですよ。そういうときには、アースの接続から自分が教える場合もあって。あとレコードでのDJの場合、針が飛びやすい。頑丈じゃないDJブースだと、お客さんが飛び跳ねると針が飛ぶっていうね。……こうやって挙げていくといろいろ不便なこともありますけど、それでもやっぱりアナログに拘っちゃいますね。多少の不便があろうと、やり慣れたスタイルに対する愛着はやっぱり根強いな」
――レコードの音質に関してはどう感じられていますか?
大貫憲章 「音は、どうですかね……レコード盤によって音は違いますし、何をもって “良い” かっていうのもありますけど。要するに、昔のレコードはモノラルの時代が一番優れていると思うんです。これらはラジオ用に作られたんですね。この頃は音が“太い”んです。とくにビートルズは素晴らしいんですよ。その後、ステレオになる前に無理矢理モノラルをステレオに分離したものも出てくるんですが、それはどうしても機械的。ヘッドフォンで片耳で音をとると、ギターしか聴こえなかったりする粗悪なものもあるので、気をつけないとヤバいなって思いますが……。そういうのはコンピレーションに多いですね。あとは、片面に12曲入ってるものなどは一枚で24曲も入っているから音圧が低かったり」
後藤 「曲数が多いと音が悪くなりますよね」
大貫憲章 「とはいえ、ちゃんと作られたレコードはもちろん問題ないですからね。……あの頃の温もりさえ感じられる60年代のシングル盤が、一番良いんじゃないかな。ちなみにビートルズのリマスターボックス(※13)が発売されたときも、ステレオよりモノラルの方が人気ありましたしね」
――一方、デジタル音源も主流となってきていますが、利便性や音質についてはどう考えられているでしょうか。
大貫憲章 「どんどんツールが便利になって、データだとより演奏の音に近いって言われてますけど、果たしてそうなのかな?とは思います。確かに音の粒立ちはクリアで、高画素のデジタル写真を眺めているような気持ちになるけれど、本当にそれが演奏している時の音なのかな? って。もっとバンドとしてごちゃごちゃしていて、アナログの音に近かったんじゃない? と。……まあ、音質の向上については、専門家の領域だからごちゃごちゃ言うことじゃないですね、究極的には僕の“好み”のことなので。極端な話、僕の知り合いにはmp3だと絶対に嫌だっていう人もいますし。結局そういう人たちは、アナログに戻って来ている」
――ダウンロードされた音源が主流になる一方でアナログ回帰の動きもあるんですね。
大貫憲章 「そうですね。ちなみにダウンロードって、ラジオで音源を使うとき以外に僕はやらないです。でもアナログ盤が揃わない場合もあるし、ノイズが入るアナログよりクリアなものを望む状況もあるし……。だから、やっぱり使い分けですよね。iTunesで買うこと自体は問題ないですけど、それはあくまで“データとして”購入してるに過ぎないっていうことを自覚して買ってほしいんだな。“音楽を買っている”というのとは違うんじゃないのかなと」

――“データを買う”ことと“音楽を買う”ことでは、大貫さんのなかで明確に違いがあるということですね。
大貫憲章 「音楽は、それを制作した人がいて、どういう意図を持っているかもインクルードして聴く作業なんだと思っているから。 “売れればなんでもいいよ”って言っている人は別だけど、そうじゃない人もたくさんいると思うので。音楽にとって“人”は一番の根幹ですからね。その人の意図、人生やバックグラウンドや土台も含めて知りたいと思うことこそが“音楽ファン”だと僕は思う。そういう意味では単にダウンロードってオススメできないですね。単に流行っているからってダウンロード音源だけ買って満足していくのは、どうなのかなって……。つまり、そのアーティストが何者なのかっていうことに興味を持ったりする間もなく消費されてしまうのは残念なんです。そんなの関係ないよ、音さえあればいいって言う人もいるかもしれないですけど、それはやっぱり“違う”と言いたい」
後藤 「はい」
大貫憲章 「たとえば僕らの世代だと、どういう曲がどういう状況でヒットしていたかをなんとなく覚えている。それが2010年代になると、これってあれのテーマ曲だったはずだけど、誰の歌だかは知らないってなっちゃう。何も音楽博士になれとはいわないけど、もうちょっと音楽に親近感を覚えてほしいなと思いますね」
――デジタル主流の世の中では、音楽への親近感が薄れてしまうのではないかと。
大貫憲章 「海外は未だにレコードを出すところも多いし、日本でも最近またレコードでリリースしたものが売れて話題になったりする。音楽を聴く上での本来の姿という意味で、レコード盤をかけることとジャケットを眺める作業は付帯すると思うんです。ジャケットがあってライナーがあれば、“プロデューサーは誰、スタジオがどこ”って自然に覚える。それが結構おもしろかったりするのに、ダウンロードでは、よほどの人でない限りわざわざ調べたりはしないでしょうから……」
後藤 「確かに」
大貫憲章 「そこまで深く知識を掘り下げろとは言わないけれど、最低、どこの国のミュージシャンでいつ頃に生まれた音楽なのかに興味を持てるような環境をなくしてはいけない。ヒット曲をダウンロードして、聴かなくなったらデリートして、っていうのは寂しいし、大袈裟かもしれないけれど、“音楽的な遺産がなくなってしまう”という印象なんです。一部のレコード会社のOBには “CDもアナログもなくなる”って言われたりもしますけど、自分としては、それは認めたくないな」
後藤 「聞きたいことを全て語っていただいた気がします……」
――本当ですね。最後に、大貫さんから、これからレコードを聴こうとする若い世代へのメッセージなどあれば。
大貫憲章 「ちょっとしたポータブルプレイヤーでも、レコードを家で聴くには十分だと思いますから。ちょっとオシャレじゃん!みたいな感じで(笑)、レコードを聴いてほしいって思います。レコードは傷がつきやすいとか汚れやすいとかありますけど、その分、愛着が沸くものなんです。だから捨てられないんですよ(笑)。聴いてないなら捨てましょうよって言われるんだけどね。2年聴いてないから捨てるっていうのは、お掃除上手な主婦の話で、レコードは人間が作った特別なものなんだよ!って(笑)。そんな音楽と人への想いを大切にしていきましょう!」

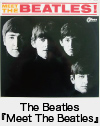
中学校くらいのときにエレキブームがあって、その渦中の二大グループですね。ベンチャーズは『LIVE IN JAPAN 65』。今はアナログは廃盤ですけど、CDも内容は一緒です。ベンチャーズが来日したときのライブを収録したもので、それを聴いたときに、すごいショックがあって。今聴いても、演奏のレベルの高さはもちろんですけど、驚くのは音質。あの時代でこんなにいいのか!?って。ビートルズは、『MEET THE BEATLES』。イギリス盤の『WITH THE BEATLES』のアメリカ盤ですけど、あの頃は国によって曲順や選曲は変わっていたので。ベンチャーズとビートルズは、僕にとって、最初のロック体験でした。
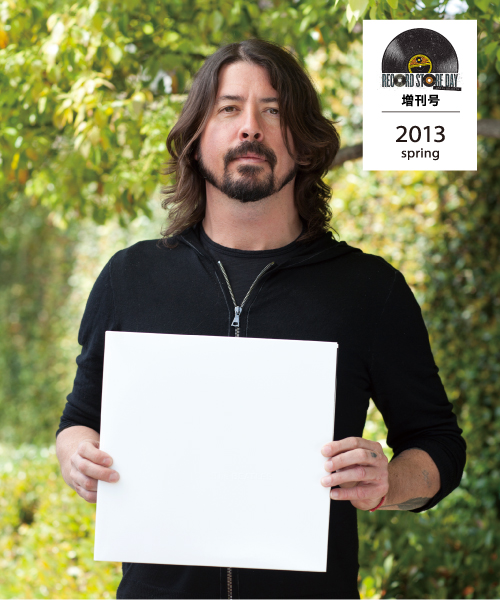

大貫憲章(おおぬき•けんしょう)
1951年東京生まれ。71年大学在学時から音楽評論家としてキャリアをスタート、当時無名のQUEENを日本にいち早く紹介したり、SEX PISTOLS,THE CLASHなどのロンドン・パンクを現地取材するなど、時代の節目節目でのキーを握る。76年、NHK-AM 『若いこだま』でラジオDJ活動も開始。79年、日本初のUKチャート専門番組となる『全英TOP20』をラジオ日本で始める。現在はInter FM『KENROCKS NITE ver.2』で相方のKatchin'とともに、選曲、構成、パーソナリ ティーの三役をこなす。さらに、80年、日本初のロックDJイベント『LONDON NITE』を新宿のディスコ『ツバキハウス』でスタート、現在も東京を拠点に各地で継続中。96年からは親交のあるDJ,Carribean Dandyや村上淳(俳優)などの親しい者たちとノン・ジャンルのDJイベント『GROOVY ROCK CARAVAN』渋谷The Roomで、ビデオ・ジョッキー的ロック・トークイベント『CROSSROADS』を渋谷Organ-Barにて継続中。さらにアメブロでブログを、Twitterでも随時発信中。
大貫憲章 twitter
■注釈
(※1)シャボン玉ホリデー
1960年代~70年代にかけて日本テレビで放映された音楽バラエティショー。一世を風靡した双子の女性歌手『ザ・ピーナッツ』が司会を務め、クレイジーキャッツがレギュラー出演、豪華なスターが毎回登場しコントや歌を披露した番組で高視聴率を獲得。昭和を代表する音楽番組といわれている。
(※2)ザ・ヒットパレード
1950年代末~70年代にかけてフジテレビで放映された生放送の音楽番組。のちに登場する数々のテレビ音楽番組の礎を築いたとされている。
(※3)ミュージックライフ
1951年~1998年にシンコー・ミュージックにより発行されていた音楽雑誌。デジタル・フリーマガジンとして2011年より復刊している。
(※4)9500万人のポピュラーリクエスト
1960年代にラジオ文化放送にて全国ネットでオンエアされていた洋楽ランキング番組。
(※5)サンレモ音楽祭
1951年よりイタリアのサンレモで毎年開催されている歌に焦点をあてたポピュラー音楽祭。かつて60年代には日本からの歌手がエントリーしたこともある。
(※6)ユーロビジョン・ソング・コンテスト
1956年以降、欧州で毎年開催されている世界的に有名な大規模音楽コンテスト。テレビ番組としても欧州全体と世界140カ国ほどで放映され、近年ではインターネット放送でも全世界へ配信されている。
(※8)白い恋人たち
1968年フランス・グルノーブルで行なわれた冬季オリンピックの記録映画『白い恋人たち』の挿入歌。映画『男と女』などでも有名なフランシス・レイによる作曲。
(※9)夜霧のしのび逢い
1944年生まれ、フランス出身のギタリスト。1964年に『夜霧のしのび逢い(スペイン語の原題:La playa)』が世界的に大ヒットした。現在は日本に帰化し、日本在住。
(※10)アラン・ドロンが主演した“太陽シリーズ”の曲
アラン・ドロンは1935年生まれ、フランスを代表する映画俳優。日本でも1960年代に人気を博し、『太陽がいっぱい』『太陽はひとりぼっち』『太陽が知っている』『地下室のメロディー』『サムライ』など彼が出演した映画のサウンド・トラックはそれだけでコンピレーション・アルバムが発売されるほどの人気だった。
(※11)サルヴァトール・アダモ
1943年生まれ、ベルギー出身の歌手・作曲家。世界的に人気があったが、とくに日本で『アダモ』の名称で親しまれ、日本語で歌った曲も多い
⇒ YouTube『アダモAdamo/雪が降るTombe la neige~日本語Version』
(※13)ビートルズのリマスターボックス
2009年にザ・ビートルズのリマスター盤ボックスセットが発売された際、限定でモノボックスも発売され、話題となった。彼らが60年代にレコードを制作した際の環境(モノラル)により忠実な音を味わいたい、というファンが多かったことを表しているといえる。